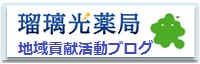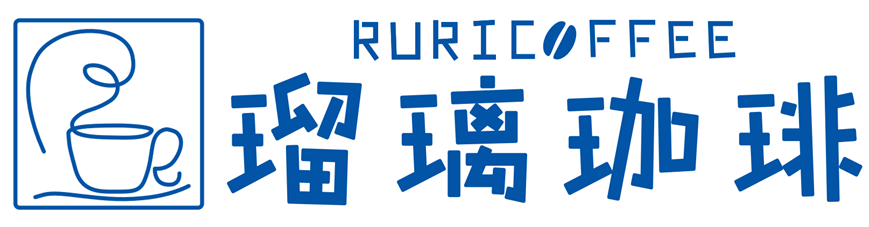口内炎
「口内炎とは」
口の中や周辺の粘膜に起こる炎症です。
その中で、特定の場所にできる場合は、歯ぐきにできれば「歯肉炎」、舌にできれば「舌炎」、唇にできれば「口唇炎」、口角にできれば「口角炎」となります。患部は潰瘍(粘膜がえぐれてできる穴)になったり水疱になったりします。
「口内炎の種類」
①アフタ性口内炎
もっとも多くみられます。ストレスや疲れによる免疫力の低下、睡眠不足、栄養不足などが考えられています。丸くて白い潰瘍が、ほお・唇の内側・舌・歯ぐきなどに発生します。小さなものが2~3個群がって発生することもあります。普通は10日~2週間ほどで治ります。
②ウイルス性口内炎
ウイルスが原因で起こる口内炎の事です。多くみられる多発性の口内炎は、口の粘膜に多くの小水疱が形成され、破れてびらんを生じることがあり、発熱や強い痛みを伴うことがあります。
③カタル性口内炎
入れ歯や矯正器具が接触したり、ほおの内側をかんでしまったりしたときの細菌の繁殖、熱湯や薬品の刺激などが原因で起こります。口の粘膜が赤く腫れたり水疱ができたりします。アフタ性とは異なり、境界がわかりづらく、味覚がわかりにくくなることがあります。
④その他の口内炎
特定の食べ物や薬物、金属が刺激となってアレルギー反応を起こす「アレルギー性口内炎」、喫煙の習慣により口の中が長期間熱にさらされることにより起こる「ニコチン性口内炎」などです。ニコチン性口内炎の場合は、口の中の粘膜や舌に白斑ができ、がんに変化するおそれもあります。
「口内炎ができたら」
ほかに持病がなく、口内炎が1カ所なら、様子をみながら、生活環境の改善を行い、ビタミン剤(特にビタミンB2)を摂りながら栄養バランスを整え、つらい症状には内服薬・塗り薬・貼り薬・うがい薬などのOTC医薬品を使いましょう。 ただし、症状が口の中全体もしくは唇や口周辺へも広がっている場合や発熱や全身倦怠感を伴う場合、症状が10日以上続く場合は病院を受診しましょう。
「口内炎の薬」
内服薬:炎症の原因物質に作用する抗炎症成分や、皮膚や粘膜を健康に保つビタミンを配合です。
スプレー薬:届きにくい患部にも手を汚さず簡単に噴射塗布できます。
塗り薬:炎症の表面に膜を作って患部を保護するため、痛みが和らぎます。
貼り薬::患部を刺激からカバーし、成分が持続的に作用します。ただし、5歳未満は飲み込む危 険があるので避けましょう。
「口内炎の予防」
*バランスのとれた食生活
偏った食生活によるビタミン不足で、口内炎が発生することがあります。緑黄色野菜たっぷりのバランスのとれた食生活を心がけ、アルコール、たばこ、香辛料は控え、ビタミンB2・B6・Cを積極的に摂りましょう。
*免疫力をアップ!
かぜや疲れなどで免疫力が落ちていると口内炎になりやすくなります。ストレスや疲れを感じたらゆっくりと休み、夜更かしなど不規則な生活を送らないようにしましょう。
*口内環境を整える
口の中の常在菌が増殖することによって、口内炎ができることもあります。口の中を清潔に保つことも大事です。
①毎食後に歯磨き・うがいをしよう
食後は、歯磨きやうがいをして、口内を清潔に。また、歯磨きの際は、口の中の粘膜を傷つけないようにしてください。
②口の中を乾燥させない
口の中が乾いていると粘膜の免疫力が低下し、口内炎になりやすいです。水やお茶で口の中を潤わせたり、あめやガムなどで唾液を分泌させましょう。
- おねしょ
- 手根管症候群
- クループ
- 糖尿病
- おたふくかぜ
- 高血圧
- 先天性魚鱗癬様紅皮症
- 胃症状
- セアカゴケグモ咬症
- サンプルA
- 変形性関節症
- 花粉症
- 手根管症候群
- 細菌性腸炎
- 水虫
- 慢性副鼻腔炎
- 蟯虫症
- 睡眠障害
- 更年期障害
- チック症
- インフルエンザ
- メタボリックシンドローム
- 片頭痛
- 口唇ヘルペス
- 高脂血症
- 高尿酸血症
- 腰痛症
- あせも
- めまい
- 骨粗鬆症
- うつ病
- 禁煙!
- バセドウ病
- パーキンソン病
- 便秘のはなし
- 緑内障
- 白内障
- いぼ
- とびひ
- 熱中症
- 帯状疱疹
- 痔
- 統合失調症
- 肺炎
- こどもの風邪
- プール熱
- 慢性閉塞性肺疾患
- 関節リウマチ
- 褥瘡
- 前立腺肥大症
- 潰瘍性大腸炎
- 疥癬
- 結核
- 不整脈
- 甲状腺機能低下症
- 甲状腺機能亢進症
- 認知症
- 気管支喘息
- アトピー性皮膚炎
- 川崎病
- 慢性肝炎
- 頭痛
- 慢性腎臓病と降圧治療
- 尿もれ
- 過活動膀胱
- エイズとHIV感染症
- 高カルシウム血症・低カルシウム血症
- 下垂体機能低下症
- 気管支炎
- ドライスキン
- 結節性甲状腺腫
- 熱性けいれん
- 夏の冷え
- ヘルパンギーナ
- 乾癬
- 下痢
- 魚の目
- 水いぼ
- 夜尿症
- 腎臓と漢方
- ロコモティブシンドローム
- ドライアイ
- 網膜剝離
- レジオネラ症
- りんご病
- ドーピング
- 過敏性大腸症候群
- 加齢黄斑変性
- クロイツフェルト・ヤコブ病
- 風邪のお話 パート1
- てんかん
- 飛蚊症
- 二日酔い
- エキノコックス症
- 麦粒腫
- 風邪のお話 パート2
- レストレスレッグス症候群
- 心筋梗塞
- 回帰熱
- 風邪のお話 パート3
- 子宮内膜症
- ビブリオ・フルビアス/ファニシー感染症
- 翼状片
- 逆流性食道炎
- 肝硬変、肝炎のお話
- 下肢静脈瘤
- シミと紫外線
- ブルーリ潰瘍
- 食事で病気を治すお手伝い~抑うつ、痴呆症~
- ウエストナイル熱/脳炎
- ピロリ菌
- 生活習慣病における運動と栄養の役割
- 口内炎
- 機能性ディスペプシア
- 不眠症
- 金属アレルギー
- かくれ脱水
- ニキビ
- ダニ媒介性脳症
- 過呼吸
- 副鼻腔炎
- ウエルシュ菌感染症
- しらみ
- 膀胱炎
- 便秘
- 前立腺がん
- ライム病
- 秋に注意したい病気と対策
- レプトスピラ症
- 体に良い食生活をするには
- ノロウィルス
- 歯周病と慢性疾患
- ガングリオン
- ハンタウィルス肺症候群
- 鉄欠乏性貧血
- 耳鳴とは
- 期外収縮
- 糖尿病性腎症
- 腸重積
- デング熱
- アナフィラキシー
- 腱鞘炎
- 睡眠時無呼吸症
- レビー小体型認知症について
- C型肝炎の新しい治療法
- 低身長
- 広東住血線虫症
- 緩和ケア
- ジアルジア症
- 溶連菌
- 尿路結石とは
- 中耳炎
- 爪白癬
- 頸肩腕症候群
- 狂犬病
- 急性出血性結膜炎
- マイコプラズマ肺炎
- 鼠径ヘルニア
- シェーグレン症候群
- 伝染性単核症
- 捻挫
- 線維筋痛症
- こむら返り
- 誤嚥性肺炎と口腔ケアについて
- 子宮頸がん
- 髄膜炎
- 急性心不全
- 歯周病
- 線維筋痛症パート2
- 腰部脊柱管狭窄症
- 脱水症
- 妊娠高血圧症候群
- アニサキス症
- 腸管出血性大腸菌
- 声帯ポリープ
- 有毒植物による食中毒
- フレイル
- RSウイルス感染症
- RSウイルス感染症
- おむつかぶれ
- はしか(麻しん)
- コクシジオイデス症
- タバコの誤飲
- 冷え性
- 手足口病
- 肺アスペルギルス症
- 風疹
- 瑠璃光薬局の由来
- 瑠璃光薬局のミッション
- 店舗紹介
- 会社概要
- 学会発表
- 在宅医療への取り組み
- 地域貢献活動
- 認定栄養ケア・ステーション
- 薬局経営塾
- 瑠璃珈琲(RURICOFFEE)
- 富山グラウジーズ×瑠璃光薬局 オリジナルお薬手帳